- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 小学2年生の「なんで学校行って勉強せんといけんのん?」に全力で答えてみた。 2017年12月公開記事
小学2年生の「なんで学校行って勉強せんといけんのん?」に全力で答えてみた。 2017年12月公開記事
2022/10/01先日、息子が
なんで学校行って勉強せんといけんのん?
と聞いてきました。
お昼にこの番組を見たようです。
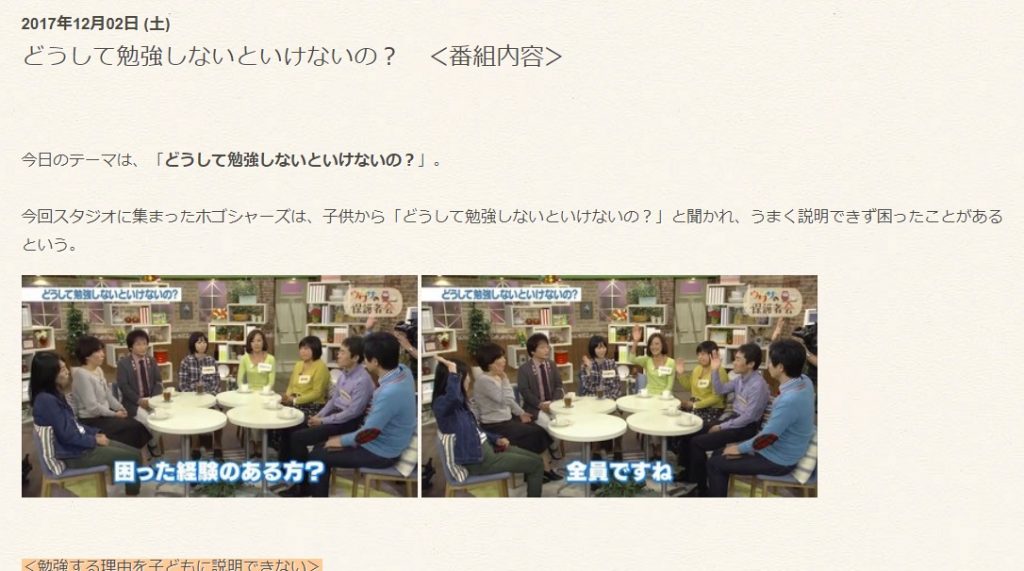
あなただったらなんと答えますか?
私はこう答えました。
良い質問じゃね~。
かあしゃんは、机に向かって紙に書くのだけが勉強じゃあないと思っとるよ。
じゃけえ、学校に行っとるとか行ってないとか関係なく、
見たり聞いたり、やってみたことが全部勉強じゃと思っとる。
じゃけぇ、必ずしも学校に行って勉強せんといけんとは思っとらんよ。
ほんじゃあ、ほんまに「やりたいことやったもんがち」(忍たま乱太郎テーマ曲)なん?
まあ、そういう部分もあると思うよ
ホリエモンはそう言っとったじゃろ
面白い楽しいてなっとるときに能力って伸びるけぇ。
ほいじゃあ、Kくん、ゲームだけやっとってもいいん?
好きじゃけぇ!
ほうじゃね。
それもありかもしれん。
じゃけど、かあしゃんは「やりたいことだけ」っていうのは違うと思う。
「やりたいことから拡げる」っていうのが一番大事だと思う。
そこからどんどん「これはなんでじゃろう」とか「ここはどうなっとるんじゃろう」って
自分で調べたり、人に聞いたりしてどんどん拡げるときに、それがその人の役に立つものになるし、楽しく勉強するっていうことになると思うよ。
そこまではわかった。
ほんじゃあ、国語とか算数とかは何の役に立つん?
国語は自分の世界を拡げてくれるんよ。
いろんなことを知ったら、ゲームでもデザインでもなんでも面白くなる。
知っとることが少ないと、面白いことが減るんよ。
Kくんは今、国語で「かさこじぞう」習っとるじゃろ?
それ知っとったら、マリオオデッセイでおじぞうさん出てきて、キャッピー(帽子)かぶせるのとか、単にかぶせるだけじゃなくて
「おじぞうさんに帽子をかぶせる」っていうのが「かさこじぞう」に似とって面白い!てなるじゃん。
そっかぁ。ほんじゃあ、算数は?
算数はいろんな意味があるよ。
1つは、計算ができると騙されにくくなるってこと。
数字はわかりやすいけぇ、世界中の人が使っとる。この数字を上手に使うと騙されにくくなる。
もう1つは、自分の気持ちとか考えを人に伝えやすくなる。
これはちょっと難しいけど、「こうしたい!」っていうのをわかりやすく伝えたら、もっともっと自由にいろんなことができるじゃろ。
で、そういうのの素になるのが小学校の算数なんよ。
数字が読めんかったら意味がない。
計算ができんかったら意味がない。
まあ、電卓使えばいいけどね。
じゃけぇ、計算が早く正確にできることよりも、なんでその式を使うんか、の方が大事なんよ。
算数はちょっとよくわからんね。
なんでよ
じゃあ、なんで子どもは学校に行って勉強せんといけんのん?
かあしゃんは、学校で勉強するのは、勉強するやり方の中でもイージーモードだと思う。
だって、何やるか、どうやるか、どの順番でやるか、どのくらいのペースでやるか、そういうの全部先生が決めて、生徒はやるだけじゃろ?
もし、それを自分でやるとしたら、子どもができそうなことを自分で探して順番も決めて、量も決めて、って全部やらんといけん。
そっちの方がハードモードじゃと思うよ。
ちょっとよくわからんけど。
Kくんは、子どもも先生になったらいいと思うよ。
みんなが好きなことを教える先生になったら楽しいけぇ。
Kくんだったら、マインクラフトとかスプラトゥーンのやり方の授業するよ。
例えば、野球が好きな子はグループ作って、一日中みんなに野球教えたらいいじゃん。
そんなんできたら楽しいじゃろうね~
いいと思うよ。
自分がわかっとることを人にもわかってもらうことってめちゃくちゃ難しいけぇ、みんなどんどんいろんな能力が高まると思うよ
いい考えじゃね。
そういう意味では、かあしゃんはあのねノート(週末の日記)が一番自由だと思うよ。
何書いてもいいんじゃけぇ。
Kくんのあのねノート、ほぼほぼゲームの話じゃん。
うん。ほうじゃね。
大人は、子どもに勉強できるようになってほしいんじゃろ?
だったら、なんで宿題とかテストとか算数の時間とか毎日(みんな)いっしょなん?
「みんなそれぞれ違うのに内容が一緒なのはなんでなんか」ってこと?
うん。
だって、子どもが知りたいことって誰が決めとるん?
そうじゃね。
それは、完全に大人の都合だけど、文部科学省っていう日本の国の小学生はこのくらい勉強しましょう、って決めるところが決めて、先生はそれに合わせとるだけなんよ。
ほんまは、一人ひとり違うのができた方がいいかもしれんけど、
まあ、全員宿題違ったら先生も準備とかチェックとか大変だし、
この子の10点とこの子の10点が同じです、って説明するのも大変なんよ。
いっぺんにたくさんの子どもたちを見るための工夫としてみんな同じものをやっとるね。
やっぱり意味わからんけど。
かあしゃんは、Kくんは毎日学校行ってよく頑張っとると思うよ。
で、こういうお話ができるのはかあしゃんはホンマに楽しいし、幸せなんよ
ありがとね~。
じゃけど、そろそろ寝ようか(おいおい、もう11時になりそうじゃないか)

(先生になって8の段の九九の授業をしてくれる息子)
とまあ、こんな感じで息子の疑問に私なりに真剣に答えてみました。
子どもの質問から逃げない、はぐらかさない、自分の考えを丁寧にわかりやすく、かつ真剣に答える。
というのが、私なりのポリシーです。
夫は、真剣に答えるけど、わかりやすくはありません。
わかりやすいかどうかは置いておいて(私も「意味わからんけど。」って言われてますし…)
子どもにとって、真剣に答えてもらうという体験は、単に知識を得るというだけでなく、
- 自分の質問は価値のあるモノ
- さらに、その質問をした自分も価値のある存在
と認識することができます。
もちろん、ここで本人は「愛されてる~」なんて意識したりはしませんけどね。
だけど、こういう何気ないところから自己肯定感というのは育ちます。
授業中ぼーっとしてるけど、鉛筆かじりまくるけど、あのねノートはかんたんなことばっかり書こうとするけど、でもこういう質問してきて、しっかり自分の考えを持っている息子に対して、私はとてもうれしいな~って感じます。
息子が賢いのではなく、
- 疑問をあしらわない
- どんな考えも否定しない
という普段があるからこそ、こんな質問が出て来るんじゃないかと手前味噌ですが思います。
一日に、1分でも30秒でもいいです。
子どもの目を見て、話を聞いてみてください。
まとめ
勉強って、なんでも全部勉強だと思うんです。
だから、学校行ってても、行って無くても勉強してる。
行ってない子は人生の辛さという勉強もやってるかもしれない。
自由を手に入れるっていうのは、自分で決めて実行できるっていうことだと思うのです。
そのために、生きる中からいろんなことを学んで自分で考えることができるように育てるのが、私達親の役割だと思っています。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい















