- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 発達障害・不登校で要望書を書くときに気をつけること 2019年3月公開記事
発達障害・不登校で要望書を書くときに気をつけること 2019年3月公開記事
2023/10/10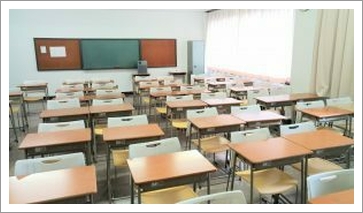
先生の異動が新聞に載るといよいよ新しい年度に向けて学校も準備が始まります。
新しい学年の先生が決まり、クラス分けや学年主任や進路指導など決まっていきます。
発達障害や不登校の子どもさんたちのことを学校にわかってもらうのは結構たいへんです。
小学校でも中学校でも、おそらく懇談のときに次年度の希望を出しているんじゃないかと思います。
が、年度末は懇談が無いこともありますから、4月1日過ぎたらまず学校に電話します。
そして、教頭先生でいいですから
今年度お世話になります〇〇です。
担任の先生が決まったら、早めに面談をさせていただきたいんですが。
と伝えて面談の予約をとりましょう。
もちろん、新学年が始まってからの最初の懇談を待ってもいいんですが、
発達障害がある子は特に「嫌な記憶」が定着しやすいもの。
なので、早めがいいです。
それから、そのときに要望書を持っていきましょう。
口頭で話したことはうまく伝わってないことが多いです。
特に中学校は関わる先生が多いし、かつての私のような講師や臨時採用の先生も多くいますから情報がちゃんと届くように文章にしておきます。
今は「合理的配慮」が学校に義務付けられていますが、
「正直、合理的配慮って何するの?」
という学校もあるんです。
「やったことないけど、やれって言われてて、
でも、やったことないから、実際なにかわからない」
ということがあるのが現実です。
なので、
うちの子、ちょっと気にかけてくれませんか
では、全くなんにも伝わりません。
書面にして
発達障害の場合は
- 脳の機能的に一度に多くのことを覚えることが困難です。口頭での指示だけでなく、黒板にも同様のことをメモしてもらえると自分でできることが増えます。
- 協調運動障害のため、目で何かを見ながら同時に身体を動かすなど、2箇所以上同時に動かすことが困難です。体育の運動テストは回数や課題の難易度など軽減していただくようお願いします。
(例としては、かなり難しい文章になってしまいました。まだまだだな~)
こんなふうに困難さとして書きます。
つい、「苦手です」と書いてしまうことがありますが、それだと「頑張ればできるんじゃない」とみられるので、「機能的な困難さ」として書くのがオススメです。
また、不登校の場合はもし対人恐怖などあれば
- 教室登校できるに越したことはないですが、教室に入れない場合は別室での登校を認めてください。
- 学校以外に学習やコミュニケーションの場「〇〇」に通っています。登校日数に入れてください。
というように、具体的にどこで何をしてほしいのかを書きます。
基本的に配慮や登校日数は校長先生の裁量です。
なので、できるできないは学校側が判断することになりますが、
「具体的に言ってもらわないと、判断のしようがない」
というのもあります。
なので、一応書いておいて、
一応、書いてみたんですけど、いかがでしょうか?
という感じだと、学校も具体的にできるできないの判断がしやすいと思います。
それに、学校とはいい関係を持てているに越したことはないので、学校に行っていようが行ってなかろうが最初はやりとりしておくといいかと思います。
まとめ
4月になったら学校に電話をして面談の約束をする。
学校には書面で出す。
要望はなるべく具体的に書く。
「苦手」の代わりに「困難」を使う。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい













