- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 「学校では楽しそうにうまくやってますよ~」のワナ 2019年10月公開記事
「学校では楽しそうにうまくやってますよ~」のワナ 2019年10月公開記事
2023/11/19登校するのがなかなか難しい子が
久しぶりに学校行ったりすると
親はたいてい心配になってて、
それを察した先生が
- 学校では友達と久しぶりに会えて楽しそうに過ごしていましたよ~
- 元気にやってましたよ~
と教えてくれる。
親は、
ああ、一人ぼっちじゃなかったんだ
と胸をなでおろすけど
次の日、子どもはすごくしんどそうに
今日は休む
って言ったりする。
こういうの、あるあるだと思うんです。
先生が見たのも事実。
本人に聞いても
思ったより、みんな優しくてよかった
って言ったりする。
それも事実。
でも、続かないのも事実。
だから、学校に続けて行けないのが
なんで?
ってなるし、
本人も
どうしてなんだろう…。
って悩んだりする。
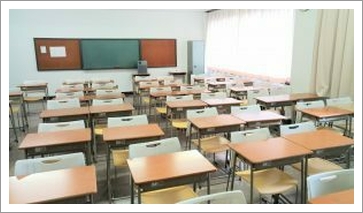
で、多分、これだと思うってのを見つけた。
今日、【お母さんのための心理学講座】でした。
9月10月は自己分析をずっとやってて
今日は「セルフモニタリング」について話しました。
セルフモニタリング力って言葉は
2通りの使われ方があります。
セルフモニタリング力
①人からどう見られているかを感知して、状況に合わせて振る舞う力
②自分の行動や考え、感情などを観察して思い返したり、記録したりする自分を感じる力
で、この①の方のセルフモニタリング力が高い人は
- 他者基準で自分の行動を決めるので「気配りができる」「気が利く」「人との結びつきを大切にする」ということに長けている。
- 「見た目を気にする」「疲れやすい」
- 役割が明確なのが好き
- 自分は周りによって態度をコロコロ変えるので自分に自信がなく感じる。
という特徴があります。
そうするとね、
学校に行くと問題なさそうに見えちゃう。
だって、周りに心配かけないようにって思ってたり
いつもどおりやってまあまあ元気なのを周りが求めていることを知っているから。
人に求められる「わたし」「ぼく」を必死でやった結果
明日は休む
今日は行かない
になったりする。
自分に求められていることがわからないと
不安でどうしたらいいかわからなくて
何もできなくなったりする。
そういうことがわかったからって、
だから何?
ってなるかもしれないんだけど、
でも、そこんとこの仕組みを知ってると
見え方が違うかな、って思う。
色んな課題・問題・状況・性格
変えられるもの
変えられないもの
いろいろあるけど
見方が変わると対応の仕方も変わるかなって思う。
もしかしたら、久しぶりに学校行くときは
すごく短くするとか
何かミッションを決めてくるとか
やることが曖昧な状況を避けるようにするとか
そういう対策をすることで
すり減ってしまうのを防げるかもしれない。
何もしなくてその場にいるだけで
アンテナ張ってがんばりすぎてしまう
セルフモニタリング力高めの子には
それなりの対応を検討する必要がありそうです。
まとめ
子どもさんがサービス精神旺盛だったり、
周りの顔色を伺うタイプだったり、
周りが楽しそうにしていることで自分は居てもいいんだって思うタイプだったら
久しぶりに行った学校で「楽しくする」っていうのが
当然だったりする。
そしたら、「頑張って」しまうよね。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい













