- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 発達障害の要素を全く持たない人はこの世にいるのか? 2019年12月公開記事
発達障害の要素を全く持たない人はこの世にいるのか? 2019年12月公開記事
2024/01/04今日の内容を一言でまとめると
発達障害の要素を全く持たない人がこの世にいるとは私には全く思えない。
なので、自分に合う手立てをいかに見つけるかが大切。
です。
発達障害を「白」か「黒」か、「ある」か「なし」かで捉えていると
辛いかもしれません。
発達障害はこういうイメージではなく
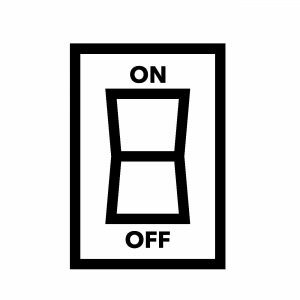
むしろ、これとか
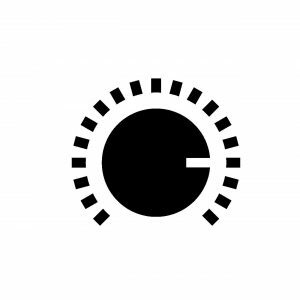
これ
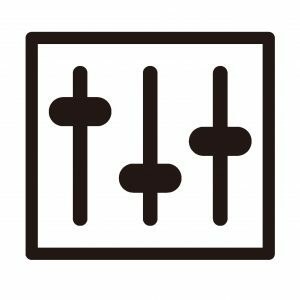
な感じ。
ほら。
果汁5%でも100%でも
どっちもオレンジジュースはオレンジジュースだし。
っていう感じです。
「じゃあ、どこから⁇」
っていうの、困りますよね?
お医者さんもやっぱりはっきりした診断基準がないと困るわけですよ。
なので、診断基準があるんですが
それもまあ、状況や社会の要請によって変化したりします。
例えば、診断基準に沿っていけば
- あと1項目✔が付けばADHDだけど、ないから
- まあ違うってことになるなぁ。
ってことだってあるわけです。
もしかしたら、
「ぎりぎり足りないけどほとんど当てはまるから診断だそう」
ということもあるかもしれません。(ないかもしれません)
だから、私は診断されていないし、行く気もありませんが、
注意欠陥的な傾向があるので、
ボリュームは大きくは出てないけど全く無いわけではない
という風に捉えていて、
そのために注意欠陥障害の人のための手立てを知り
その中から自分に合うものを使うようにしています。
ていうか、
全然なくて無色透明な人なんか居ない!
というのが私の見解です。
さて、そう考えると
「発達障害の診断」をどう考えるか?
というのは、その人やその周りの人に委ねられている部分があります。
だって、診断に関わらずその人の「能力」や「特性」や「困っていること」、「得意なこと」は変わらないわけですから。
発達障害だから、この子は大変な子なんだ
というよりは
てことは、これが得意で、これが苦手なのか!!
苦手なことは、どんな方法があるかな。
という
- 手立てを考えるための材料が手に入った状態
といえると思います。
なので、診断が受験での措置や学校での合理的配慮を得るための手段になるような場合の他に
自分を知るため(子どもさんを知るため)の材料として
使うのがいいんじゃないかと私は考えています。
こちら、片づけ・家庭教師・ピアノ教師の宮丸しおり※さんのブログです。 ※2024年1月現在もライフオーガナイザーかどうかは確認できていません
当事者の母でもあるしおりさんの捉え方、手立ての立て方はとても参考になります。
まとめ
診断が出たら、ツイッターで検索してみたらいいと思います。
いろんな人がいろんな工夫をしています。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい















