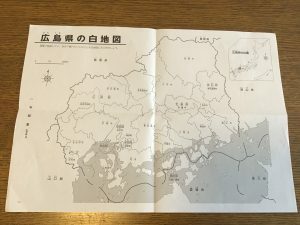- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 自主的に勉強する子どもの育て方〜引き算の子育て2 2020年3月公開記事
自主的に勉強する子どもの育て方〜引き算の子育て2 2020年3月公開記事
2024/01/12この記事の続きです。
今日の内容を一言でまとめると
「引き算の子育て」とは
環境を整えるのがとても大切!!
つまり「環境調整」の賜物だ!
です。
今回の引き算の子育ては、空間の引き算。
子どもに注目してほしいことを目立たせるには、
その他を減らして、「分かりやすくする」ことが必要だったりします。
前回も今回も、決して
うちの子すごいでしょ!!
って言う記事じゃないんです。
誰でもできるけど、
知らないとできないことを
本当にやったら
自分から勉強する子が出来つつありますよ
というお話です。
前回は
「環境を整えたら自分で勝手にやってたよ。」
という話でした。
環境を整えるというのは
- その子にとってやりやすい方法
- やろうと思った時にすぐに始められる準備
というのが本当に大切です。
なので、環境調整は「自主的に勉強する子を育てる」のに絶対に外せないです。
そこをうまくやるとこんなふうに自分で集中して勉強する子になります。

その環境とは何かを、分析してみると
- 環境「空間」を整える
- 環境「人の反応」を整える
の二つでした。
どちらも、かなり小さい頃からやっているので、
それを遡ってご紹介しようと思います。
まず、なにかやろうと思ったときの鉄則は
アクセスに20秒以上かかってはダメ
です。
そのためにできる
環境調整「空間」
をご紹介します。
①見えるところに配置する
子どもは小さければ小さいほど、一時的に覚えておく脳の容量が少ないので、【見えない=ない】になりがち。
なので、見えるところに置きます。

②モノを減らして「ある」ことを分かりやすくする
モノがたくさんありすぎるとそれはノイズです。
そして、子どもには風景になります。
風景をわざわざ手に取ることはしませんね。
なので、子どもに何か呈示するときは「片づけ」必須です。

と言っても、子どもいたら仕方ないところもあるんですけどね。
まあ、できる程度でやってみるのがいいかなと思います。
モノが減ると分かりやすいので
「指示が明確に通りやすくなる」
そうすると、お互いにストレスも減ります。
片づけ苦手な人はこちらどうぞ↓
ちなみに5月に全国で片づけのイベントあります。
私は、息子が3歳の時にライフオーガナイズを学んで、とても良かったです。
そして、2つ目
環境「人の反応」を整える
です。
人間が1番やっかい。
それは、子どもの世界に勝手に入って価値観を入れていくから。
まあ、それも社会性だし、
まっさらに育てることは難しいし、
なんなら、子育てには「社会のルールを教える」という大切な役割があるので、
絶対入っちゃダメ!!ってわけではないんですが、
でも、子どもの邪魔をすることもしばしば。
次回は人間をどうするか?
の話にします。
まとめ
子どもが自分から勉強するのには、
実は地道な作業が必要だったりします。
今回の引き算は空間の引き算。
子どもに注目してほしいことを目立たせるには、
その他を減らして、「分かりやすくする」ことが必要だったりします。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい