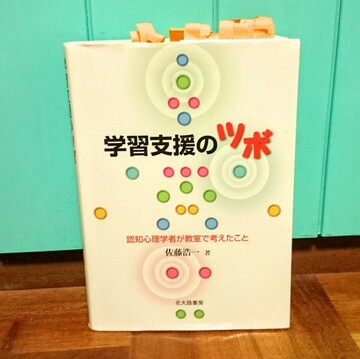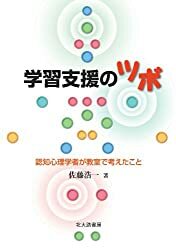- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 生徒の学習効果を高めたい先生にオススメの本 2016年7月公開記事
生徒の学習効果を高めたい先生にオススメの本 2016年7月公開記事
2022/07/16今日は本のご紹介
【内容】
小中学校の授業について、認知心理学者が考えた大切なポイント(ツボ)を、
できるだけ学術用語などは使わずに、現場の先生方に語りかける。
頭の働き、メタ認知、指示・発問・説明、グループ学習、道具、やる気、テストや評価などを取りあげる。
【Amazonより引用】
画像クリックでAmazonに飛びます。
中学校で毎日数学の授業をしていた時、この本を知っていたら、もしかしたら生徒たちの成績はもっとあがっていたかも知れない。
そのくらい、なんとなくではなく「指導や工夫の理由を理論的に知る」ということは大切だし、
多くの教育現場では欠けているんじゃないかと思います。
というのも、学校の先生って職人さんみたいなところがあるなぁ、と常々感じています。
ある先生の良い指導をマネするとか、学び合いとか、研究授業とか、結構多くされています。
が、科学的な根拠があるというよりは見て学べ…的な…。
みんな一人ひとり独自のやりかたを構築するんですが、一人ひとりの力量にゆだねられているんですよね…。
(だから、あたりはずれが…)
例えば、私の行っていた中学校では、授業の始まりに「瞑目」つまり授業の開始時に目をつむって、心を落ち着ける時間を取ることをやっていたんです。

が、誰も一度も生徒にその効果を科学的な理由をつけて説明しているのを見たことはありません。
(私が知らないだけで、やっていたんかもしれんけど)
だから、本来瞑目は
「集中力を増して、判断力や思考力をあげる」効果的な方法なんだけど、
誰も説明しないから生徒は知らない
知らないから使う場所がわからない
それで、本当に効果があるのかなぁ。
そんな気はしていました。
そこで、3年生には、受験もあるし面接で緊張することもあるので、
瞑目の効果と、する理由、一緒に簡単な注意の向ける方法も教えていました。
そうすると
「先生入試の時やったらほんまに落ち着いてできたよ」という報告を何人もしてくれました。
効果を知っていたからこそ使えたと思います。
知らなかったら思い出せなかったんじゃないかな…
授業はあんまり落ち着いたものにはならなかったけど…。
という訳で、この本は、人に何かをレクチャーする人にオススメしたい一冊。
「授業をもっと効果的なものにしたい」
「もっとうまい学習方法が知りたい」
「受講生の定着率を高めたい」
そんな誰かに何かを教える人だけでなく
「子どもがもっと勉強がわかるようになる方法がしりたい」お母さんやお父さん、
「学習の効果を上げたい」と思っている中学生・高校生にも、オススメの一冊です。
内容は心理学のお話ですが、とてもわかりやすいし言葉も簡単だし、具体例も多くイメージしやすかったり
自分の生活の中に落とし込みやすい内容になっています。
私も、来週の看護学校の授業でやってみま~す。
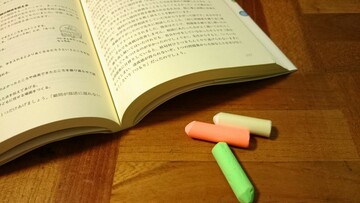
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい