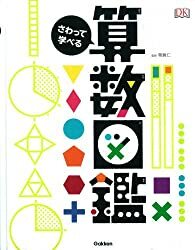- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 算数が楽しくなる本 2017年6月公開記事
算数が楽しくなる本 2017年6月公開記事
2022/09/17算数好きですか?
何人もの生徒を教えていて「わかる」への道筋が、子どもによって2種類に別れるな、と思います。
①理屈がわかると進めるタイプ
このタイプはとにかく「どうしてそうなっているか」がわからないとすすめない。
なので、「え?そんなところで?」というようなところでつまづいていることがあるので、
わかりやすく仕組みを理解できるように説明するのが大事です。
②パターンをある程度習得させると理屈がわかるタイプ
こちらのタイプは理屈は後回し。
ひとまず、パターンを身体に覚えさせて、後から仕組みを説明するようにすると、なるほどとなるタイプ。
先に仕組みや理屈を教えると、混乱してわけがわからなくなりがちです。
身体に覚えさせていくのが大事。
私達大人も、掛け算の仕組みって実は理解してませんよね。
2×5と5×2って実は違うんですよ。
2×5は2+2+2+2+2という意味。
5×2は5+5という意味。
だから、小学校では
クッキーが2枚入った箱が5箱あります。クッキーは何枚ですか?
だと、式は2×5=10となり、5×2=10ではやり直しになることがあるんですね。
でも、そんな説明ができる親がどのくらいいるでしょうか??
中学では乗法の交換法則によって2×5も5×2も同じものとして扱われます。
その辺がひたすら具体物のみを扱う算数とは違うところです。
で、 ①と②、どちらの種類の子どもさんだったとしても、生活の中で数字や数、長さや重さに触れておくのはとても大切です。
なぜなら、中学までの算数・数学はイメージがとても大切だからです。
円柱の体積だったら輪切りのきゅうりが◯センチ重なっているイメージ。
速さや水溶液といった単位あたりの量を考えるときも、
道を同じ速さで進むイメージや、水に食塩を溶かすイメージができて絵がかければときやすくなります。
そういうのは、日々の生活の中で少しずつ取り入れることができます。
例えば小さい子なら、
- いちごやプチトマト、ぶどうなどを家族の人数分のお皿を出して均等にわけさせたり、
- レゴを組み立てるときにポチの数を2✕2で4ポチと表現したり、
- お風呂のタイルを数えてみたり
そんなちょっとしたところに算数を入れてみると、子どもは学校でならった時に
「あ、なんか知ってる」と思えるのです。
しっかり読むわけではないですが、こんな本もいいですね。
「学研 算数図鑑」
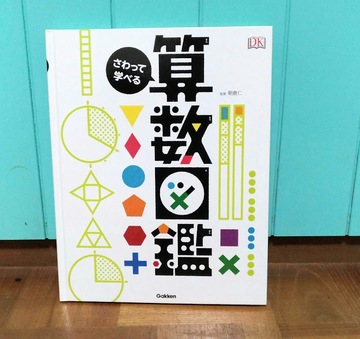
この本のいいところは、立体図形が本のまま作れるところです。
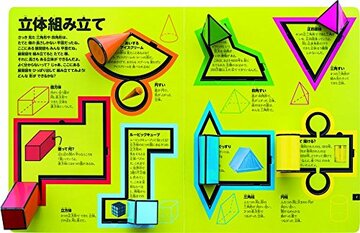
分数はこんな感じ。
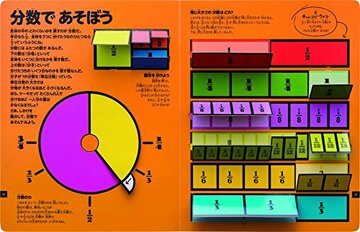
しかけ絵本みたいで楽しいです。
わかってなくてもいいんです。
まずは、身近に感じるところから。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい