- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 発達障害って、みんな学んだ方がいいんじゃないの?! 2017年10月公開記事
発達障害って、みんな学んだ方がいいんじゃないの?! 2017年10月公開記事
2022/09/18先日、息子が私の仕事部屋に来て並べてある本を見ながら
かあしゃん、発達障害ってなんなん?
と聞いてきました。
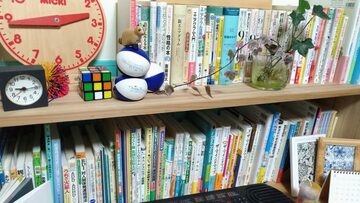
小学2年生にわかりやすく発達障害を説明する…。
かあしゃんは、頭の中にやらんといけんことを覚えとくのが苦手だったり、
あと、おっちょこちょいですぐモノを落としてしまったりするところがあるんじゃけど、
Kくんはそういう困ることとか、難しいこととか、苦手なことない??
う~ん、そうじゃねぇ。暗いのとか大きい音が怖いのとか?
そういうのの中で、頑張ったり、慣れたり、練習したりしてもできるようにはならんものってあるじゃん。
例えば、Kくんが映画館が怖いのって別に頑張ったけぇってできるようにはならんじゃろ?
完璧な人間っておらんけぇ、みんな何かしら苦手なこととかあって、
それの中で努力とか練習ではみんなと同じくらいにはならんのがあるのが発達障害かねぇ。
Kくんの周りにも色んな人がおるじゃろ?
じいちゃんとかばあちゃまはお耳がだんだん聞こえんようになってきたり、目が見えんようになってきとるしね。
みんな色々あるじゃん。
そういうのの中で、人の気持ちがわかりにくいとか、お勉強で漢字がなかなか覚えられんとか、
大きな音が怖いとか、人がいっぱいおるとしんどくなるとか、聞いたことをすぐ忘れてしまうとか、そういう人もおるんよね。
そういうので困ったり、お手伝いが必要だったりする人のことを発達障害って言うんよ。
ふ~ん。そうなんじゃ~。
かあしゃんは、みんな何かしらの発達障害を持っとると思うんよ。
じゃけぇ、工夫したり助けてもらったり、みんながしたらいいと思う。
じゃけぇ、かあしゃんが助けてって言ったら助けてほしいし、
Kくんが助けてほしいときとか、工夫したいけどどうしたらいいかわからんときは聞いてほしいな、って思うよ。
なかなか難易度の高い問いでした。
息子が全部理解できたとは思えませんが、少しずつまた機会があるごとに伝えたいと思った出来事でした。
そして、自分自身をよくよく理解しようと努力していると、人との違いに対してとやかく言うことが減る、と私は思っています。
というのも、
以前やっていた「自己分析ワークショップ」で自分のことをいろいろな角度から分析するという、
グループで2週間に1回のワークを2年位続けると「なんだか人に優しくなれるようになってきた」という人がすごく増えたんです。
3グループくらいやったらどのグループでも半分くらいの人が同じことを言うんです。
中にはそうならない人もいるんですが、それでも何かしらの変化があるんです。
なので、
- 他人に不満がある人
- しょっちゅう文句を言っている人
- 人を思い通りにしたい人は、
自己分析をしてみるのをおすすめします。
そうすれば、発達障害が特別なものではなくて、多かれ少なかれ自分の中にも似たような特性があることがわかると思います。
そうすれば、言い方や伝え方、受け取り方を工夫することができます。

多くの人は、誰かの発信したことばやしぐさを、シチュエーションや場の雰囲気で必要以上に読み取り過ぎているのかもしれません。
そして、それが当たり前になりすぎると、他者にも要求してしまいます。
発達障害はけっして他人事ではなくて、誰もに関係することであり、
学んでおくといろいろと工夫するときのヒントもたくさん見つかってラクになれることがあるのです。
そうは言っても、私もまだまだわからないことがたくさんあります。
どうかいろいろ教えてください。
発達障害が身近になってきた昨今。
他人事ではなく、自分のラクな生き方のためにも学んでおくととても便利です。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい















