- ホーム
- きらぼし学舎 過去ブログ
- 授業に集中できない子 2017年11月公開記事
授業に集中できない子 2017年11月公開記事
2022/09/19学校で授業をしていると、話を聞いていない生徒というのは本当に困ります。
「指示が通らない」というのは教師として非常に緊急かつ重要な問題です。
話を聞いていない子よりももっと困るのは、喋りたい衝動を抑えられない子です。
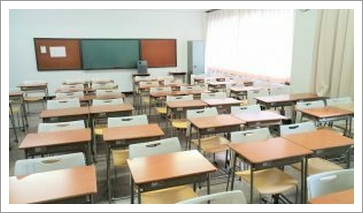
看護学校や短大では
「みなさんはもう大人だし、目的をもって学びを選択してこの場にいるので、私は私語を注意したりしません。
自分で自分の行動をコントロールしてください。」
と、一番はじめの授業で話します。
ですが、これが親の立場だと全然ものの見え方が違います。
昨日の息子の授業参観で、授業を受ける息子の様子を見ていて、もしかしたら価値観が違うのかな~と思いました。
先生の指示をよく聞いて、ノートを素早く書き、質問を考え、手を挙げて先生の指名や○を待つ子どもたち。
かたや
聞いとるんか聞いとらんのかよくわからんが、一応椅子には座っていて、周りより1分くらい遅れてノートを書き始め、
友達の発表も聞いとるんか聞いとらんのかよくわからん感じで、
でもたまにアンテナに引っかかることがあるらしく、手を挙げて発表することもあったり、
自分の考えを見せあいこして互いのサインをもらう時間には途中から、どんだけ面白いサインをつくるか!に目的が変わっている。
そんなうちの息子を見て多少動揺しつつ、「去年よりマシか」、と思い「ああ、私とは違う価値観なんだな。」と感じたのでした。

(廊下に飾ってあった息子の絵。前は雑なのが気になっていたけど、この躍動感が好きだなと思えるようになった。)
思えば、中学校で教壇に立っていたときは、
『いかにクラスを落ち着かせて一人ひとりが授業に集中して聞くという状態を作るか』
ということをいつも考えていました。
生徒を惹き付ける授業を作らないと、学びは始まらないから。
それに、一生懸命学んでいる子どもの権利も守ってあげたかったから。
その時は、純粋にそれだけを考えていたけれど、本当はそうではなかったのかもしれない。
と昨日思いました。
というのも、やはり私の中に動揺する気持ちがあったからです。
授業中に先生や友達の話を漏らすまいと聞いて、かつノートを素早く書き、きびきびと行動するといった
「自分の中であって欲しい息子の姿」は見られなかった。
そして、未だにそんな息子は見たこと無いのに、
それでもそうであってほしいとどこかで願っている、そんな自分に気づいたからです。
確かに、きびきびと動く子どもたちはキラキラして見える。
だけど、
「もしかしたら「承認欲求」が高いタイプなのかな。」とも思えました。(あくまでも私の感想ですが。)
承認欲求の高い子どもたちは「褒められること」に価値があると感じていて、
それは親がいれば親、先生がいれば先生、場所によってそれはコーチだったり、監督だったり、その場での統率者が誰なのかを素早く察知して
そこに「認めてもらう」という形にそぐうよう自己を変化させる。
私がまさにそうでした。
そういう子は確かに扱いがラクなんです。
それこそ、アメとムチをはっきり使い分ければいいから。
でも、そうじゃない子は扱いにくい。
承認以外のところで惹きつけないといけないから。
帰って息子に聞きました。(たいていお風呂に入っているときか寝る前におしゃべりします。)
ねぇねぇ、Kくん。
かあしゃんは今日Kくんが授業受け取るの見て、なんかすごいな~って思ったよ。
かあしゃんだったら、先生に褒められたい気持ちでノート書いたり発表したりするけど、Kくんはなんか違っとったけぇ。
Kくんねぇ、算数ちょっと苦手なんよ。
あ、そうなん?単位換算とかすぐできるし、かあしゃんよりセンスあると思うよ。
そういうのは好きじゃけど、他のはあんまり、なんか違うんよね~。
そうなんじゃ~。大学行ったら、自分の好きなところだけ勉強できるよ。
ほうなん?それならいいかも。
どうやら、算数に苦手意識があるらしい。
息子が苦手なのは算数じゃなくて、きっと書いたり指示に従ったりだと考えました。
- わかる=楽しいということも知っている。
- だから、できることは嬉しいし楽しい。
- 先生に褒められたい気持ちもある。
だけど、意識をコントロールするのが難しいから、授業では聞き漏らしが増え、
気分で意識をコントロールしたりしなかったりしていることに気づいていない。
息子のような子は、
きっと私達が
- 大勢の人が行き交う空港で英語を話す人と会話することになり、一生懸命聞き取ろうとするんだけどところどころしかわからない、
- ドラマを見ているときに横で子どもが騒いでいて、一生懸命聞き取ろうとするんだけど、よくわからない
というのと同じくらいの集中力とエネルギーをつかってしかも、よくわからんっていう感じになっています。
じゃあ、集中力はどうやってアップさせるか?
マルチタスクをしようとしない。
つまり、あれもこれもではなく、1つずつやるようにする。
家では、指示をいっぺんに出さないようにします。
出すとしたら、一つずつメモさせたり、チェックリストを渡すようにする。
気になることを減らす。
それから、短期記憶を鍛える。
キーワードを復唱させる。
授業では難しいかもしれませんが、お家ではできることもあります。
気が散る原因になるものを減らせば、子どもの気が散りにくい環境を作っていくことになります。
例えば、
- 食事中にはテレビを切る。
- テレビにカバーをつける。
- 何かをしながら、別の何かをする、というのを減らす。
- 勉強をするときには、勉強をする場所に行く。
- 集中すべきときには話しかけない。
- 子どもが考えているときには待つ。
そんな小さいことをもう少し積み重ねてみようと思います。
息子に私の価値観を押し付けず、もう少し行動を見てみようと思ったのでした。
まとめ
子どもがどう行動するかを全てコントロールすることはできません。
でも、子どもは子どもなりに成長していて、それを邪魔しないのも親の仕事です。
おそらく、日本は授業というものの在り方を変えるべき時期に来ているんだと思います。
先生が生徒の興味を引くという時代では無い気がします。
でも、学校での時間が長い子どもたちにこそ、わかりやすい情報と環境を少なくとも家だけでも準備してあげることで勉強がどんどん嫌いになったり、学校に行くのが嫌になったりということは減らせるかもしれません。
今日も読んでいただきありがとうございます。
-
 夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
夏休み小学生向けオススメ問題集 2019年7月公開記事
夏休みに子どもがやる問題集でオススメなのない?と、ステキなご質問をいただいたので、ご紹介しますね!小学生の場合
-
 子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!何を育てるか? 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
子どもにゲームをやめさせたい!困った時がチャンス! 2015年4月公開記事
子どもにゲームをやめさせたい!ゲームって本当に悪なの? 2015年4月公
-
 私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
私の失敗!ゲームのルール編 2016年1月公開記事
今日のポイントたまにはキレることもある!!またもや息子にしてやられました。昨日の夕方家庭教師に行く前、息子は動
-
 子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい
子どものゲームのルールづくりはこれで守りやすくなる! 2015年12月公開記事
今日のポイント言葉は消えるけど 字は消えない!!最近、息子と夫が連日のように ハリー・ポッターシリーズを見てい















